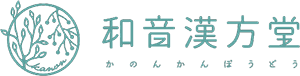ぐるぐる、天地が動いて身動き取れず、吐き気も伴うものからふわふわ浮いたように感じのもの
まず、検査も必要
めまいのなかには、急を要する「脳梗塞や脳腫瘍、水頭症」など
心配な病気が隠れている場合も有ります。
あまりに酷い場合や繰り返すなら1度検査をしておきましょう。
その上で、
・原因が分からないのに度々繰り返す。
・忘れた頃に又おこる。
・軽いけれど続いている。
・寝不足や疲れでおこる。
そんな場合には、体質から探って漢方薬を試してみることをオススメしたいと思います。
漢方医学から見るめまいの種類
めまいは漢方医学において体のバランスが崩れた結果として現れる症状の一つです。
原因によっていくつかのタイプに分類され、それぞれに適した漢方薬や養生法があります。
タイプ1
ストレスやイライラ、自律神経の乱れによって起きるめまい
肝陽上亢(かんようじょうこう)タイプ
急なめまいが起きた原因を振り替えると
ストレスが一番思い当たる…。
という方も多いのでは。
時に喜び過ぎたり、興奮しすぎたりでもバランスを崩します。
激しいめまいの他、頭がふわふわする、顔がほてる、耳鳴りがする、目の充血や頭痛を伴うことも
【漢方的解釈と対策】
「肝」という臓器は気血を巡らせる役割があります。ストレスや怒りで「肝の陽気」が過剰になり、
上に昇ることでめまいが生じます。熱を冷まし、肝の興奮を鎮める
竜胆瀉肝湯(竜胆瀉肝湯)や羚羊角(れいようかく)などの入った漢方薬を選択します。
タイプ2
水分代謝が悪くて起きるめまい
痰湿中阻(たんしつちゅうそ)タイプ
「水毒」と言う先生も居ますが
近年では、「水」より更に粘りけのある「痰湿」が関連するめまいを多くみます。
ふわふわするめまいや、ボーッとする、頭が重苦しい、胃の不快感や吐き気を伴うことも
普段から胃腸の弱い方は特に起こしやすいめまいです。
【漢方的解釈と対策】
体内の「痰湿」(余分な水分や老廃物)が停滞し、頭に影響を及ぼすことでめまいが生じます。
半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)や苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)など、
胃腸の働きを高め、水分代謝を高める漢方を使います。身体の中に溜まった痰湿を取り除き、
水分代謝を促し、めまいを改善します。
タイプ3
元気や血液が充実せず起こるめまい
気血両虚(きけつりょうきょ)タイプ
気(エネルギー)と血(栄養)が不足すると、脳に十分な栄養が届かず、めまいが起こります。
疲れや睡眠不足、生理中や後にも起きやすい傾向が有ります。
【漢方的解釈と対策】
心脾顆粒(しんぴかりゅう)婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)などで
気血を補い、心脾や全身を滋養します。
しっかりよい血液や元気を補って予防もしていきましょう。
タイプ4
加齢から起こるめまい
腎精不足(じんせいぶそく)タイプ
加齢によるめまいで、耳鳴りや腰痛、足のだるさを伴う事も多く、記憶力の低下を感じることも
【漢方的解釈と対策】
「腎」は生命エネルギーの源であり、加齢とともに衰えると、脳や耳に必要なエネルギーが不足し、めまいが生じます。
六味地黄丸(ろくみじおうがん)や杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)など
で、腎を補い、老化による症状を改善しつつ、めまいや目や耳の不調を整えます。
タイプ5
血流が悪くおきるめまい
血流が悪いために、脳血流の低下などから起きやすいめまいです。肩凝りや頭痛を伴ったり、血圧の高い方も。
血瘀(けつお)タイプ
頭が締め付けられるようなめまいや後頭部痛、肩凝り、を伴うことが多いタイプです。中には、舌の色が暗く、瘀点(おてん)が見られます。
【漢方的解釈と対策】
血の巡りが悪くなり、脳への血流が滞ることでめまいが生じるため、血流改善の漢方を選択します。
冠元顆粒(かんげんかりゅう)や芎帰調血飲第一加減などの脳や心臓、又全身の血流を改善し、瘀血を除きめまいを改善します。
まとめ
めまいは、高血圧や更年期などの様々な原因が絡み合って起こることも有ります。
その時も自分の体質を見極めることが大切で、漢方では「どのバランスが崩れているか」に着目します。
長年、辛いめまいに悩まされ、ようやく漢方でスッキリした。など、自分の事がよく分かり、めまいを改善できたという例もあります。
普段からの食事や生活習慣も重要です。
例えば
肝陽上亢タイプ→ カフェイン・辛いものを控え、香りのよいもの(柑橘類やシソ、セロリなどの香味野菜)を食したり、リラックスタイムを取れるように。
気血両虚や腎虚タイプ→消化のよい 栄養のある食事(黒ごま、クコの実、ナツメなど)を意識する、睡眠をしっかりとる。
痰湿中阻や血瘀タイプ→ 油っこいものや甘いものを控え、適度な運動で水分代謝を促す
自分は、どのタイプのめまいか一緒に見極めながら、適した漢方と養生を組み合わせていきましょう!